2025/09/09

現代では「説教」と聞くと、学校の先生や親の小言を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、「説教」と「小言」は、まったく次元の異なるものです。本来の「説教」とは、文字通り“教えを説く”ことであり、人を咎めて文句を言うことではありません。では、教えを説くとはどういうことなのでしょうか。
かつては「説教」の「教」を「経」と書いて「説経」と呼び、経典の内容を解説して人々を教化することを意味していました。ところが、明治時代に教部省が「説経」を「説教」と書き換え、禅宗の説法や真宗の法談などを一括して「説教」と呼ぶようになったのです。
お役所が宗教の内部に立ち入ることには賛否あるでしょうが、仏教の要義を信者に宣説するという点では共通しているため、この変更も一理あると言えます。
つまり、「説教」とは仏教を説くことであり、それ以外の何物でもありません。
🪷仏教の三法印に学ぶ
仏教の教えには「三法印」と呼ばれる三つの柱があります:
①諸行無常:すべてのものは移り変わり、常に変化している
②諸法無我:すべての存在には固定した「我」がない
③涅槃寂静:煩悩を離れた静かな心の境地
これらを一言で表すならば、「すべては移り変わってとどまることがなく、それは自然の大法則によるものである。だからこそ、個人のわがまま勝手は許されず、この大法則たる真理と一体になることこそ、煩いのない心そのものになる道である」と言えるでしょう。
本物の説教を聞くために
今日では「説教」と聞くと、まず学校の先生や親の小言のことを思い出す人が多いよう
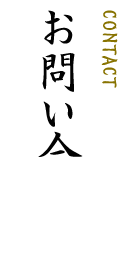
お問い合わせやご質問等についてはこちらよりお願いいたします。
また、毎月の鬼子母神講(毎月8日 午後7時)や七面さま講(毎月18時 午後2時~)へのご参加も
心よりお待ちしております。
日蓮宗 妙栄山 法典寺
〒418-0023 静岡県富士宮市山本371-1
Tel.0544-66-8800
Fax.0544-66-8550