2025/03/07

最近、人間が倣慢(ごうまん)になり、おこがましくも大自然を征服すると称して開発を 行ない、逆に大自然から「しっぺがえし」を受けて、さまざまの災害に見舞われているようです。乱開発による洪水や落盤事故、工場から出る汚物による病気、一酸化炭素による地球の温暖化、等々…。このままいきますと、最後には大自然の威力によって人間が滅亡する日を迎えることにもなりかねまよんね。
さて、「しっぺがえし」を漢字で書きますと、「竹篦がえし」となりますが、この「竹篦」とは何でしょうか。これを文字通りに受けとめれば、単なる竹製のへらということになりますが、実際にはへらと言うよりは杖のことで、禅宗で用いる法具の一つです。
竹を割って三尺ほどの長さに切り、これを合わせて籐を巻き、漆を塗って作りますが、昔は師家(師匠・教師)が学人を教導する時に用いられ、時にはこれで打って大悟徹底させようとしたものなのです。今では法戦式の時に、首座と呼ばれる大衆の代表が形式的に用いるだけのものになっておりますが、この竹篦はただの杖ではありません。這箇(しやこ)は是れ三尺の黒蜿蛇(こくがんじや)、昔日(そのかみ)霊山(りようぜん)に在っては金波(こんぱ)羅華(らけ)となり又少林に伝えては五葉となる。或時んば則ち龍と化して乾坤(けんこん)を呑却(どんしやく)し、或時んば則ち宝剣と作って殺活(せつかつじざい)自在(じざい)。
という拈(ねん)竹篦(しつぺい)の法語のとおり、毒蛇にも金蓮華にもなり、梅の花にも龍に も、宝剣にもなる。そのようにして私たちを大悟に導いてくれる有難い法具なのです。
しかし、もし私たちが生意気を起こしてこの竹篦をふるえば、偉大な相手は逆に私たちを悟らせようと、もっと強い力で竹篦を返してくるでしょう。本当の真心をもって竹篦をふるうのでなければ、竹篦がえしを受けて自らの非を悟ることになります。
どんな世界に於ても、およそ人の先に立ち教導にあたるものは、くれぐれも倣漫にならぬよう、竹篦の使い方を心得たいものであります。
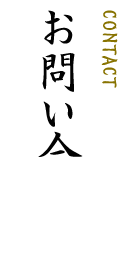
お問い合わせやご質問等についてはこちらよりお願いいたします。
また、毎月の鬼子母神講(毎月8日 午後7時)や七面さま講(毎月18時 午後2時~)へのご参加も
心よりお待ちしております。
日蓮宗 妙栄山 法典寺
〒418-0023 静岡県富士宮市山本371-1
Tel.0544-66-8800
Fax.0544-66-8550